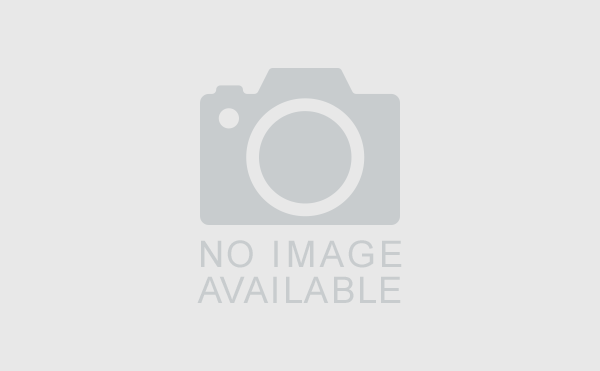フィードバックが下手な日本人
「言わずとも伝わる」は日本特有の文化
少子高齢化による労働人口の減少により、さまざまな業界で外国人労働者が増えていることを肌で実感する今日この頃です。
外国人は多言語を話せる場合が多く、また業務を習得しようという熱意にあふれている人も少なくなく、働き手不足解消の一端を担っています。
しかし、彼らは外国で生まれ育ち、日本とは異なる文化や習慣のもとで人格が形成されているため、日本人とは異なる価値観や常識のもとで発言したり行動したりすることになります。これにより日本人との間でいわゆる「異文化衝突」が生じることがあります。
マネジメント層の方々は当然、外国人労働者に対しても彼らの仕事ぶりへのフィードバックが必要になります。日本の職場におけるフィードバック事情について考える時、まず頭に浮かぶのは「言わずとも伝わる」文化です。この「高コンテクスト文化(※1)」特有のコミュニケーションスタイルは、日本社会に深く根付いています。これは特に外国人労働者から見ると、時に「フィードバックが少ない」「評価が曖昧」といった不満や不安につながることがあるようです。
私は会社員時代に22年間の海外駐在(イタリア、カナダ、中国、ドイツ)を経験しており、「異文化衝突」にはずいぶんと苦しめられストレスを感じてきました。外国人とともに働き、成果をあげるためには、その国の言語を習得すること以上にその国の文化や価値観を理解することが大切だと感じます。
日本で働く外国人たちも自国と異なる日本の文化や習慣に戸惑い、そしてどう対処してよいか悩み苦しむことが少なくないのではないかと思います。
「フィードバック」における文化的な違い
たとえば、欧米の職場ではポジティブ・フィードバック(褒める)もネガティブ・フィードバック(問題の指摘)も非常に直接的で頻繁です。「いい仕事だったね!」「次回はこのように改善した方がいいよ!」といった具体的な言葉が飛び交います。
一方、非言語的なコミュニケーションを好む日本では、上司が面と向かって部下の行動を褒めることは少ないでしょう。「仕事はできて当たり前」と考えていたり、「褒めると努力しなくなる」と考えてしまったりすることもあるため、部下の仕事に問題がなければ、特段何も伝えないことが多いと思います。また、部下の仕事ぶりに問題があれば、上司はオブラートに包んだ表現を使い、それとなく問題を指摘します。むしろ、部下のほうが上司の意図を察し、自分で改善策を考えるべきだ、という空気があります。
外国人労働者の視点
来日した外国人労働者、特に欧米出身の人からすると、日本でのこのコミュニケーションは時にミステリアスです。彼らは成功した時の称賛、失敗した時の具体的な指導を期待します。しかし、それがない場合、モチベーションの低下やストレスにつながることも少なくありません。
言語による直接的なコミュニケーションを好む人は、フィードバックを当然の行為だと考えているからです。上司からのフィードバックがなければ、「自分は無視されている」「大切にされていない」と解釈してしまう可能性もあるのです。
なぜ日本人はフィードバックが苦手なのか
直接的なコミュニケーションを好む人のなかでも、特に優秀な人は過去にたくさんのポジティブなフィードバックを受けてきたはずです。ところが、日本企業に入った途端、ほとんどフィードバックがない状態になります。すると、自分は評価されていないと感じ、この企業に自分の将来はないと考え、辞めてしまう人もいます。こうした誤解により企業にも本人にもとても残念な結果になることもあるのです。
部下が望ましくない行動を続けているとき、日本人に多い傾向は「いつか自分で気づき、直してくれるだろう」と期待することです。しかし、直接的なコミュニケーションを好む人は、ネガティブ・フィードバックを行わなければ、自分から行動を変えることはありません。
部下としてはフィードバックがないのは自分に悪い点はないからだ、と考えます。しかし、前述のとおり、非言語的なコミュニケーションの環境で育った日本人には外国人が期待する直接的なフィードバックは苦手となりがちです。
ネガティブ・フィードバックの基本ステップと実践ポイント
ネガティブ・フィードバックには3つの基本ステップがあります。
1.問題行動を指摘する
2.望ましくない行動がもたらした結果や影響を指摘する
3.今後どのような行動をとってほしいかを伝える
この基本ステップのなかの1番目のステップにおける実践ポイントは、指摘する内容は客観的な事実だけに絞り、「単純なミスをして」など人格を否定するような感情を含んだ表現を使うと相手も感情的になり、論点が別の方向に外れてしまいます。何が問題であったかについて、事実だけを分かりやすく指摘するのです。
そして、2番目のステップにおける実践ポイントは、「なぜ、その行動が望ましくないのか」に関する理由の説明です。日本的な感覚で指導を行う場合は、「皆まで言わなくても分かるだろう」という意識が働きがちです。しかし、「相手は日本の文化の当たり前を知らない」という前提に立ち、具体的に説明することが大切になります。
日本には「叱る」という言葉があります。多くの国では、叱るとは親から子どもに向かうものであり、大人同士には馴染まないと考えられています。荒い言葉遣いや感情的な表現は相手の自尊心を傷つけ、人間関係にも悪い影響を与え、パワーハラスメントにもなりかねません。事実と問題点を指摘しながらも相手の感情を傷つけないよう、敬意を込めた表現を用いるようにしましょう。
むすびに
ポジティブ・フィードバックは些細なことでも頻繁に、ネガティブ・フィードバックはタイミングを逸することなく、そして丁寧に。日本で働くことを選んでよかったと感じてもらえるようなコミュニケーションを心がけたいものです。
(※1)世界には「高コンテクスト文化(察しの文化)」と「低コンテクスト文化(言葉の文化)」の型が存在する。「高コンテクスト文化」は実際に言葉として表現された内容よりも言葉にされていない内容のほうが豊かな伝達方式で、アジアを主としたコミュニケーションスタイル。とりわけ日本人は「以心伝心」や「空気が読める」などと表現されるなど、世界で最も「高コンテクスト文化」の国と言われている。一方、「低コンテクスト文化」は、言葉に表現された内容のみが情報としての意味を持ち、言葉にしていない内容は伝わらないとされる。欧米諸国を主としたコミュニケーションスタイル。
文責:小林正光
投稿者プロフィール
最新の投稿
 診断士の経営相談コラム2026年1月27日「活力」を「利益」に変える投資戦略
診断士の経営相談コラム2026年1月27日「活力」を「利益」に変える投資戦略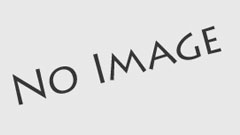 お知らせ2026年1月1日2026年 新年のご挨拶
お知らせ2026年1月1日2026年 新年のご挨拶 診断士の経営相談コラム2025年12月2日インフレ時代の流動資産活用法
診断士の経営相談コラム2025年12月2日インフレ時代の流動資産活用法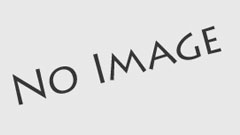 お知らせ2025年10月1日2025/11/19 セミナー開催のお知らせ
お知らせ2025年10月1日2025/11/19 セミナー開催のお知らせ